 Random Note Random Note
2002年SCP日本代表 川越俊美さんに決定
(『日本歯科評論(Dental Review)』10月号に掲載された内容を転載したものです.)
|
2002年SCP日本代表 川越俊美さんに決定
|
8回目を迎えた日本歯科医師会/デンツプライ(米国)SCP (スチューデント・クリニシャン・プログラム)の平成14年度日本代表選抜大会が,去る8月28日,新歯科医師会館において開催され,神奈川歯科大学6年生の川越俊美さんが優勝した.川越さんは10月19日から米国ニューオリンズで開かれる第143回ADA年次総会大会におけるSCPおよび関連行事に招待され,世界各国より参加したクリニシャンと共に発表を行う(各発表内容は以下の抄録を参照).
|
|
|
|
|
| 受賞後,喜びの表情の川越俊美さん(神奈川歯科大学6年生)とファカルティーアドバイザーを務めた佐藤貞雄神奈川歯科大学教授(歯科矯正学講座). |
上位入賞者.真ん中が優勝した川越さん,右が2位の名護さん(徳島大歯3年生),左が3位の葛西さん(日大松戸歯3年生).今大会より,優勝者には優勝杯が授与されることになった. |
|
[優勝]
|
ブラックスチェッカーを用いた睡眠ブラキシズム時のグラインディング運動パターンの分析
川越俊美さん(神奈川歯科大学6年生) |
 一般的に睡眠ブラキシズムは,夜間における顎機能運動と考えられている.睡眠時のブラキシズム運動は強力な咬合力を発揮し,歯の磨耗や歯周組織の破壊,顎関節の機能障害さらに咀嚼筋の異常活動を誘発する原因となっている.今回,睡眠時のブラキシズム運動を簡便に評価する方法を開発したので,その効果について報告する.被験者の上顎石膏模型に,ポリビニール製0.1mm厚のシートを加熱圧接して,ブラックスチェッカーを作製し,被験者に2日間就眠時に装着させた.各被験者の下顎頭の運動経路を調べるために,アキシオグラフを用いて運動を採得した.被験印象採得を行い,硬石膏模型を作製し,SAM咬合器に付着し,その咬合状態を観察した.グラインディングパターンは,ICPから始まる広い楕円形の後退運動として観察された.咬合誘導様式はCanine Dominance Grinding (CG), Canine Dominance Grinding with Balancing Grinding (CG+BG), Group Grinding (GG), Group Grinding with Balancing Grinding (GG+BG) の4つのカテゴリーに分類された.ブラックスチェッカーを用いることで,睡眠時のブラキシズム運動を評価し,機能的に調和した咬合の再建に応用できることが示唆された. 一般的に睡眠ブラキシズムは,夜間における顎機能運動と考えられている.睡眠時のブラキシズム運動は強力な咬合力を発揮し,歯の磨耗や歯周組織の破壊,顎関節の機能障害さらに咀嚼筋の異常活動を誘発する原因となっている.今回,睡眠時のブラキシズム運動を簡便に評価する方法を開発したので,その効果について報告する.被験者の上顎石膏模型に,ポリビニール製0.1mm厚のシートを加熱圧接して,ブラックスチェッカーを作製し,被験者に2日間就眠時に装着させた.各被験者の下顎頭の運動経路を調べるために,アキシオグラフを用いて運動を採得した.被験印象採得を行い,硬石膏模型を作製し,SAM咬合器に付着し,その咬合状態を観察した.グラインディングパターンは,ICPから始まる広い楕円形の後退運動として観察された.咬合誘導様式はCanine Dominance Grinding (CG), Canine Dominance Grinding with Balancing Grinding (CG+BG), Group Grinding (GG), Group Grinding with Balancing Grinding (GG+BG) の4つのカテゴリーに分類された.ブラックスチェッカーを用いることで,睡眠時のブラキシズム運動を評価し,機能的に調和した咬合の再建に応用できることが示唆された. |
|
[2位]
|
遠隔歯科医療システムを用いた教育支援
名護太志さん(徳島大学歯学部3年生)
|
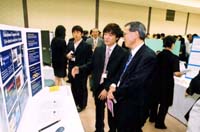 現在,インターネットは多角的に学習手段を結びつけ,新しいインタラクティブな教育環境を実現しようとしている.そこで,学生に要求される膨大な知識に対するアプローチとして,医学・歯学教育においてもe-learningを積極的に用いることを提唱したい.今回,学生の立場から,インターネットを介して,大学病院と地域の開業歯科医師との間で特に医療画像についてのカンファレンスを行うことを目的として開発された遠隔医療システムを学生教育支援へと応用した.本システムによるe-learningの試行を教員3名(小児歯科歯科医師)および,学生10名を対象として行った.システム利用許可を受けた学生は,いつ,どこからでも,画質の高い症例画像情報にアクセスでき,講義時間外でも,効率的に症例情報を検索・閲覧できた.症例画像を基に学生同士または教員を交えてのディスカッションをインターネット上で開催することもできる.教員側としては学生側の弱点・盲点等が容易に発見できるようになり,それをレポート学習におけるe-teachingや実際の講義に反映することにより,インターネットを用いた双方向教育が行えるということが示唆された. 現在,インターネットは多角的に学習手段を結びつけ,新しいインタラクティブな教育環境を実現しようとしている.そこで,学生に要求される膨大な知識に対するアプローチとして,医学・歯学教育においてもe-learningを積極的に用いることを提唱したい.今回,学生の立場から,インターネットを介して,大学病院と地域の開業歯科医師との間で特に医療画像についてのカンファレンスを行うことを目的として開発された遠隔医療システムを学生教育支援へと応用した.本システムによるe-learningの試行を教員3名(小児歯科歯科医師)および,学生10名を対象として行った.システム利用許可を受けた学生は,いつ,どこからでも,画質の高い症例画像情報にアクセスでき,講義時間外でも,効率的に症例情報を検索・閲覧できた.症例画像を基に学生同士または教員を交えてのディスカッションをインターネット上で開催することもできる.教員側としては学生側の弱点・盲点等が容易に発見できるようになり,それをレポート学習におけるe-teachingや実際の講義に反映することにより,インターネットを用いた双方向教育が行えるということが示唆された.
|
|
[3位]
|
新規口臭除去物質の研究
葛西理恵さん(日本大学松戸歯学部3年生)
|
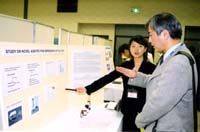 口臭は,その不快な感じから,広く認識されることがらのひとつである.一般的に,口臭の原因物質として揮発性含硫化合物があげられ,それは口腔内に存在する細菌によってタンパク質が分解されてできるものであることが知られている.そこで,この揮発性含硫化合物を低下させることにより,口臭を減少させることを試みることにした.含硫化合物の定量には,Halimeterを用いた.最初,含硫化合物と反応して不溶性,無臭の硫化亜鉛を形成する亜鉛化合物による試験を試みた.塩化亜鉛の溶液で処理することにより,揮発性含硫化合物の濃度を低下させることはできたが,塩化亜鉛の純粋なものをヒトに用いることは好ましいことではないと考えられた.そこで,食品または健康食品の中で亜鉛含量の多いものをインターネットで検索し,カキエキスが亜鉛を多く含有することを発見した.In vitro 試験でカキエキスが揮発性含硫化合物の濃度を低下させることを見出し,ヒトを対象にしたin vivo 試験でも,カキエキスが有効であることを見出した.したがって,口臭を除去するための洗口剤の成分として,カキエキスを用いる可能性が示唆された. 口臭は,その不快な感じから,広く認識されることがらのひとつである.一般的に,口臭の原因物質として揮発性含硫化合物があげられ,それは口腔内に存在する細菌によってタンパク質が分解されてできるものであることが知られている.そこで,この揮発性含硫化合物を低下させることにより,口臭を減少させることを試みることにした.含硫化合物の定量には,Halimeterを用いた.最初,含硫化合物と反応して不溶性,無臭の硫化亜鉛を形成する亜鉛化合物による試験を試みた.塩化亜鉛の溶液で処理することにより,揮発性含硫化合物の濃度を低下させることはできたが,塩化亜鉛の純粋なものをヒトに用いることは好ましいことではないと考えられた.そこで,食品または健康食品の中で亜鉛含量の多いものをインターネットで検索し,カキエキスが亜鉛を多く含有することを発見した.In vitro 試験でカキエキスが揮発性含硫化合物の濃度を低下させることを見出し,ヒトを対象にしたin vivo 試験でも,カキエキスが有効であることを見出した.したがって,口臭を除去するための洗口剤の成分として,カキエキスを用いる可能性が示唆された.
|
|
4-META/MMA-TBBレジンセメントの引き抜き試験
熊谷直大さん(新潟大学歯学部4年生)
|
 各種レジンセメントの取り扱い説明書では,補綴物の合着時においてセメントが完全硬化する前に余剰セメントを除去することを推奨している.しかし,完全硬化前,すなわち餅状期の4-META/MMA-TBBレジンセメントは粘弾性が非常に高いため,マージン部余剰セメントを除去した場合,マージン内部のセメント層を引きずり出す危険性が考えられる.そこで,その影響を調べる目的で実験を行った結果,マージンの適合が悪いと,また被着面が水で濡れていると,餅状期の余剰セメント除去よるセメント層の欠損が大きくなる可能性が高いことが示唆された. 各種レジンセメントの取り扱い説明書では,補綴物の合着時においてセメントが完全硬化する前に余剰セメントを除去することを推奨している.しかし,完全硬化前,すなわち餅状期の4-META/MMA-TBBレジンセメントは粘弾性が非常に高いため,マージン部余剰セメントを除去した場合,マージン内部のセメント層を引きずり出す危険性が考えられる.そこで,その影響を調べる目的で実験を行った結果,マージンの適合が悪いと,また被着面が水で濡れていると,餅状期の余剰セメント除去よるセメント層の欠損が大きくなる可能性が高いことが示唆された.
|
|
患者は歯科治療の何に恐怖を抱いているか?─日本,フィリピン,タイ,U.K.における検討─
上杉篤史さん(日本歯科大学新潟歯学部4年生)
|
 安全で快適な歯科治療を提供するためには“歯科治療の何に恐怖を抱いているか”を調査することが不可欠であり,国際化という意味においては国民性の差異を認識することも重要と思われる.そこで,本学および姉妹校でアンケート調査を実施した結果,日本では半数以上が抜歯を最も嫌いな処置に挙げており,歯科治療に対する不安感と抜歯処置の密接な関連が伺われた.また日本とイギリスでは処置が嫌いな理由として恐怖心を挙げる人が最も多く,フィリピンとタイでも2番目に多かった.これにより,今後は心理的要因への対策も重要であることが伺われた. 安全で快適な歯科治療を提供するためには“歯科治療の何に恐怖を抱いているか”を調査することが不可欠であり,国際化という意味においては国民性の差異を認識することも重要と思われる.そこで,本学および姉妹校でアンケート調査を実施した結果,日本では半数以上が抜歯を最も嫌いな処置に挙げており,歯科治療に対する不安感と抜歯処置の密接な関連が伺われた.また日本とイギリスでは処置が嫌いな理由として恐怖心を挙げる人が最も多く,フィリピンとタイでも2番目に多かった.これにより,今後は心理的要因への対策も重要であることが伺われた.
|
|
姿勢および噛みしめ強さの違いによる咬合接触状態の変化
西村美千代さん(東京医科歯科大学歯学部6年生)
|
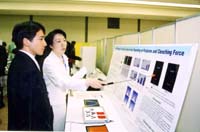 間接法による歯冠補綴物の作製では,通常,試適時に咬頭嵌合位より200〜300μm 程度高くなるため咬合調整が必要となっており,それを仰臥位で行うことがある.そこで,座位と仰臥位の両姿勢において,噛みしめ強さを変化させた際の咬頭嵌合位における咬合接触状態を比較し,仰臥位での咬合調整の妥当性について検討した.その結果から,片顎臼歯部の咬合接触の無い患者はもとより,咬頭嵌合位が安定している患者でもある程度の咬合力が負荷されないと咬頭嵌合位は安定しない可能性があり,咬合調整をする際には座位で行うことが望ましいと考える. 間接法による歯冠補綴物の作製では,通常,試適時に咬頭嵌合位より200〜300μm 程度高くなるため咬合調整が必要となっており,それを仰臥位で行うことがある.そこで,座位と仰臥位の両姿勢において,噛みしめ強さを変化させた際の咬頭嵌合位における咬合接触状態を比較し,仰臥位での咬合調整の妥当性について検討した.その結果から,片顎臼歯部の咬合接触の無い患者はもとより,咬頭嵌合位が安定している患者でもある程度の咬合力が負荷されないと咬頭嵌合位は安定しない可能性があり,咬合調整をする際には座位で行うことが望ましいと考える.
|
|
試作薄型マウスガードの着用により選手の運動能力は向上する
関根陽平さん(昭和大学歯学部5年生)
|
 危険度の高い7つの競技において試合中のマウスガード(MG)着用が義務化されているが,その使用状況および選手の意識を調査・検討した.また,従来型(5mm)より薄型の試作MG(<3mm)を処方し,競技中の変化についても調査した.結果,練習中のMG着用率は競技・種目で差があり,試作MGは従来型に比べ呼吸・発声しやすく,練習中のMG使用率が上昇したことから,練習中のMG着用率の低さは従来型MGの不快事項に起因することが判明した.試作MGは従来型の問題点を解消し,選手の運動能力を向上させることが示唆された. 危険度の高い7つの競技において試合中のマウスガード(MG)着用が義務化されているが,その使用状況および選手の意識を調査・検討した.また,従来型(5mm)より薄型の試作MG(<3mm)を処方し,競技中の変化についても調査した.結果,練習中のMG着用率は競技・種目で差があり,試作MGは従来型に比べ呼吸・発声しやすく,練習中のMG使用率が上昇したことから,練習中のMG着用率の低さは従来型MGの不快事項に起因することが判明した.試作MGは従来型の問題点を解消し,選手の運動能力を向上させることが示唆された.
|
|
Actinobacillus actinomycetemcomitans バイオフィルム形成因子の解析
齋藤貴之さん(東京歯科大学6年生)
|
 本研究では,歯周炎患者からのA.a.の検出率はprobing depthの増加に伴って上昇すること,患者から分離した菌株にはrough型集落が多いこと,rough型菌体には強いバイオフィルム形成能があることを明らかにした.さらに,バイオフィルム形成能と線毛関連性rcpAとrcpB遺伝子発現の関係を解析した結果,rough型菌株にはrcpAとrcpBの発現が認められるが,smooth型はほとんど発現しないことを見出した.これらの結果から,A.a.の線毛関連性遺伝子は,本菌が歯周局所でバイオフィルムとなって定着するために重要な役割を果たしていると考えられる. 本研究では,歯周炎患者からのA.a.の検出率はprobing depthの増加に伴って上昇すること,患者から分離した菌株にはrough型集落が多いこと,rough型菌体には強いバイオフィルム形成能があることを明らかにした.さらに,バイオフィルム形成能と線毛関連性rcpAとrcpB遺伝子発現の関係を解析した結果,rough型菌株にはrcpAとrcpBの発現が認められるが,smooth型はほとんど発現しないことを見出した.これらの結果から,A.a.の線毛関連性遺伝子は,本菌が歯周局所でバイオフィルムとなって定着するために重要な役割を果たしていると考えられる.
|
|
インスリン様増殖因子シグナルと咬筋表現型の変化
横山香里さん(鶴見大学歯学部5年生)
|
 飼料形状によるマウス咬筋の表現型の変化にインスリン様増殖因子(IGF)が関与するかを調べた.マウスを離乳直後から固形飼料で飼育し,6カ月齢に達した時点で液状飼料に変え,さらに1週間飼育したところ,マウス咬筋のミオシン重鎖IIb(最も速筋型)mRNA発現量が増加していた.これは液状飼料に転換して1週間飼育したマウス咬筋に速筋化が起きたことを示している.また,液状飼料に転換したマウス咬筋のIGF-IおよびIImRNA発現量は共に減少していた.この結果より,IGFsの減少がマウス咬筋の速筋化と関係している可能性が示唆された. 飼料形状によるマウス咬筋の表現型の変化にインスリン様増殖因子(IGF)が関与するかを調べた.マウスを離乳直後から固形飼料で飼育し,6カ月齢に達した時点で液状飼料に変え,さらに1週間飼育したところ,マウス咬筋のミオシン重鎖IIb(最も速筋型)mRNA発現量が増加していた.これは液状飼料に転換して1週間飼育したマウス咬筋に速筋化が起きたことを示している.また,液状飼料に転換したマウス咬筋のIGF-IおよびIImRNA発現量は共に減少していた.この結果より,IGFsの減少がマウス咬筋の速筋化と関係している可能性が示唆された.
|
|
ホワイトニングが歯科用金属修復物におよぼす影響
柘植琢磨さん(日本大学歯学部5年生)
|
 ホワイトニング材の適用が金属修復物の電位挙動におよぼす影響について,歯科用金属合金を用いて検討を加えるとともに,実験の内容を理解し協力を得られた被験者の口腔内金属修復物について測定を行った.結果,使用したいずれの歯科用合金においても過酸化水素によって電位が貴になり,酸化が進むことが示された.また,口腔内における測定でも,過酸化尿素の適用によって貴になる傾向を示したところから,過酸化水素は歯科用金属に作用して酸化を進行させることが判明した.本研究から酸化を防止する保護材の開発が急務であることが示唆された. ホワイトニング材の適用が金属修復物の電位挙動におよぼす影響について,歯科用金属合金を用いて検討を加えるとともに,実験の内容を理解し協力を得られた被験者の口腔内金属修復物について測定を行った.結果,使用したいずれの歯科用合金においても過酸化水素によって電位が貴になり,酸化が進むことが示された.また,口腔内における測定でも,過酸化尿素の適用によって貴になる傾向を示したところから,過酸化水素は歯科用金属に作用して酸化を進行させることが判明した.本研究から酸化を防止する保護材の開発が急務であることが示唆された.
|
|
お茶抽出液や漢方成分は,細菌内毒素によるNO産生促進を阻害する
岡安晴生さん(明海大学歯学部4年生)
|
 LPSによるマクロファージ活性化に伴うNO産生に及ぼす漢方成分と各種天然化合物の効果を,新たに作成した評価系(50%細胞障害濃度(CC50),NO産生の50%抑制濃度(EC50),有効係数(SI=CC50/EC50))を用いて比較検討した.漢方成分群は総じて細胞毒性は弱く,また,LPSによるNO産生促進を効率的に抑制した.これは呉茱萸湯において特に顕著であった.茶の抽出液群,及び各種新規天然化合物群では,多くが細胞障害活性を示す濃度でLPSの活性を抑えた.結果,漢方成分はLPSによって惹起される炎症反応を抑制することが期待される. LPSによるマクロファージ活性化に伴うNO産生に及ぼす漢方成分と各種天然化合物の効果を,新たに作成した評価系(50%細胞障害濃度(CC50),NO産生の50%抑制濃度(EC50),有効係数(SI=CC50/EC50))を用いて比較検討した.漢方成分群は総じて細胞毒性は弱く,また,LPSによるNO産生促進を効率的に抑制した.これは呉茱萸湯において特に顕著であった.茶の抽出液群,及び各種新規天然化合物群では,多くが細胞障害活性を示す濃度でLPSの活性を抑えた.結果,漢方成分はLPSによって惹起される炎症反応を抑制することが期待される.
|
|
歯ブラシと舌ブラシが口臭に与える影響
永井裕子さん(朝日大学歯学部4年生)
|
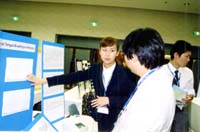 口腔に起因する口臭の原因である歯垢,舌苔に対し,歯ブラシと舌ブラシを行うことで,口臭に対しどの様な影響を与えるかを検討した.1日の口臭値(硫黄化合物:VSC)変動を口腔内清掃しない状態で,健康な被検者に対し計測した結果,起床時,食事後2〜3時間後に高い値を示すことが明らかになった.そのことから,昼食後口腔内清掃なしで2時間経過した時点で口臭を測定し,歯ブラシのみあるいは歯ブラシと舌ブラシを行う群とで,その後の低い口臭状態の持続を比較,検討したところ,舌ブラシの併用は低い口臭を持続することに効果的であった. 口腔に起因する口臭の原因である歯垢,舌苔に対し,歯ブラシと舌ブラシを行うことで,口臭に対しどの様な影響を与えるかを検討した.1日の口臭値(硫黄化合物:VSC)変動を口腔内清掃しない状態で,健康な被検者に対し計測した結果,起床時,食事後2〜3時間後に高い値を示すことが明らかになった.そのことから,昼食後口腔内清掃なしで2時間経過した時点で口臭を測定し,歯ブラシのみあるいは歯ブラシと舌ブラシを行う群とで,その後の低い口臭状態の持続を比較,検討したところ,舌ブラシの併用は低い口臭を持続することに効果的であった.
|
|
光触媒を含有した歯磨剤の開発
小南理美さん(愛知学院大学歯学部5年生)
|
 歯のホワイトニングを目的に,アナターゼ型二酸化チタンを含有した新しい歯磨剤の開発を試みた.光触媒作用を有するアナターゼ型二酸化チタンを合成し,そのX線回析パターンを作成後ピーク分析を行い,粉末X線データーブックをもとに同定し,本実験の試料として使用した.作成した歯磨剤をコーヒー,紅茶や食用色素で染色した布に塗布,紫外線を照射し,一日後,染色した布の脱色を測定した.結果,アナターゼ型二酸化チタン配合歯磨剤は優れた脱灰効力を持ち,また誰もが家庭で簡便に用いる事が可能なホワイトニング方法であることが示唆された. 歯のホワイトニングを目的に,アナターゼ型二酸化チタンを含有した新しい歯磨剤の開発を試みた.光触媒作用を有するアナターゼ型二酸化チタンを合成し,そのX線回析パターンを作成後ピーク分析を行い,粉末X線データーブックをもとに同定し,本実験の試料として使用した.作成した歯磨剤をコーヒー,紅茶や食用色素で染色した布に塗布,紫外線を照射し,一日後,染色した布の脱色を測定した.結果,アナターゼ型二酸化チタン配合歯磨剤は優れた脱灰効力を持ち,また誰もが家庭で簡便に用いる事が可能なホワイトニング方法であることが示唆された.
|
|
テトラサイクリン歯の漂白は可能か
朴 玲子さん(大阪歯科大学5年生)
|
 テトラサイクリン着色歯に対する漂白処理の可能性を,牛歯によるディスク試料とハイドロキシアパタイト(HA)板を用いてin vitroで調べた.ΔE(色の変化)はディスク,HA板とも1回目の漂白処理においてのみ変化した.L*値(明るさ)はHA板で1回目の漂白処理においてのみ上昇するが,ディスクでは全ての漂白処理で変化しなかった.C*値(鮮やかさ)は1回目の漂白処理においてのみ,両方で低下した.結果,テトラサイクリン歯への漂白処理は有効であることがわかったが,漂白処理回数の増加が漂白効果の増大につながることは認められなかった. テトラサイクリン着色歯に対する漂白処理の可能性を,牛歯によるディスク試料とハイドロキシアパタイト(HA)板を用いてin vitroで調べた.ΔE(色の変化)はディスク,HA板とも1回目の漂白処理においてのみ変化した.L*値(明るさ)はHA板で1回目の漂白処理においてのみ上昇するが,ディスクでは全ての漂白処理で変化しなかった.C*値(鮮やかさ)は1回目の漂白処理においてのみ,両方で低下した.結果,テトラサイクリン歯への漂白処理は有効であることがわかったが,漂白処理回数の増加が漂白効果の増大につながることは認められなかった.
|
|
結合組織成長因子(CTGF)定量解析のためのELISAシステムの開発と応用
川木晴美さん(岡山大学歯学部5年生)
|
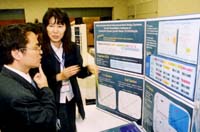 CTGFの様々な機能の解析のために,各種モノクローナル抗体を組み合わせ,3種のELISAシステムを確立した.それぞれの特徴は,1.CTモジュールとVWCモジュールを認識し,全長CTGFを測定するもの(全長CTGFの定量・解析に有用),2.N末端部のIGFBPモジュールとVWCモジュールを認識して全長CTGFを測定するもの(CTGFが断片化されて機能すると考えられる場合での解析に有用),3.VWCモジュールのみを認識し全長CTGFは認識しないもの(CTGFの断片化と,VWCモジュールを含む断片の動態を解析するのに有用),である. CTGFの様々な機能の解析のために,各種モノクローナル抗体を組み合わせ,3種のELISAシステムを確立した.それぞれの特徴は,1.CTモジュールとVWCモジュールを認識し,全長CTGFを測定するもの(全長CTGFの定量・解析に有用),2.N末端部のIGFBPモジュールとVWCモジュールを認識して全長CTGFを測定するもの(CTGFが断片化されて機能すると考えられる場合での解析に有用),3.VWCモジュールのみを認識し全長CTGFは認識しないもの(CTGFの断片化と,VWCモジュールを含む断片の動態を解析するのに有用),である.
|
|
唾液腺カルシウム濃度の測定によるカリエスリスクテストの開発
金剛寛泰さん(広島大学歯学部6年生)
|
 唾液カルシウム濃度はカリエスリスクファクターの一つと考えられるが,その測定は煩雑である.そこで,飲料水用カルシウム試薬であるEBTを用いると滴定操作におけるEDTA量によってカルシウム量を算出できることを利用し,唾液カルシウム量を簡単に評価する方法の開発を試みた.報告されている唾液内カルシウム量に近似する5種類のカルシウム溶液の色を赤から青へ変化させるのに必要なEDTA量から唾液カルシウム量への変換表を作成し,これにより5種類の唾液内カルシウム量が簡単に評価できるようになった. 唾液カルシウム濃度はカリエスリスクファクターの一つと考えられるが,その測定は煩雑である.そこで,飲料水用カルシウム試薬であるEBTを用いると滴定操作におけるEDTA量によってカルシウム量を算出できることを利用し,唾液カルシウム量を簡単に評価する方法の開発を試みた.報告されている唾液内カルシウム量に近似する5種類のカルシウム溶液の色を赤から青へ変化させるのに必要なEDTA量から唾液カルシウム量への変換表を作成し,これにより5種類の唾液内カルシウム量が簡単に評価できるようになった.
|
|
デジタルX線撮影における画像データの光減衰への対応
坂口 賢さん(福岡歯科大学4年生)
|
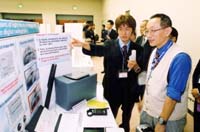 イメージングプレート(IP)方式のデジタルX線画像装置に使われるプレートは,照度650luxの室内光10秒の露光で48%に,光減衰による画像劣化が認められた.この光減衰への対応策として,遮光シートでプレートを被覆する方法を考案した.これにより撮影後のプレートは一度も室内光に曝されることなく画像化出来るようになった.人骨ファントムのパノラマX線写真を撮影,遮光シートを使用しなかった場合との画像の比較検討を行った結果,プレート遮光シートを用いることにより,通常の明るさで操作しても画像の劣化はみられなかった. イメージングプレート(IP)方式のデジタルX線画像装置に使われるプレートは,照度650luxの室内光10秒の露光で48%に,光減衰による画像劣化が認められた.この光減衰への対応策として,遮光シートでプレートを被覆する方法を考案した.これにより撮影後のプレートは一度も室内光に曝されることなく画像化出来るようになった.人骨ファントムのパノラマX線写真を撮影,遮光シートを使用しなかった場合との画像の比較検討を行った結果,プレート遮光シートを用いることにより,通常の明るさで操作しても画像の劣化はみられなかった.
|
|
廃棄ガラスの再利用による歯科用グラスアイオノマーセメントの試作
篠崎昌一さん(九州大学歯学部5年生)
|
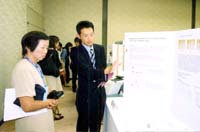
廃棄ガラスの再利用によるグラスアイオノマーセメントの作製を試みた.市販グラスアイオノマーセメントの組成から考慮し,粉砕した廃棄ガラスに硬化に必要なAl2O3およびCaF2を加え,1400℃での溶融によりセメント用ガラスを調製した.作製したガラス粉末を市販セメント液で練和し,硬化性を調べた.硬化した試作セメントは,Al2O3,CaF2の配合比により操作性,硬化時間は大きく変化し,圧縮強度は約500kg/cm2で市販セメントより劣っていた.実用化にはさらなる検討が必要だが,廃棄ガラスからセメントの作製が可能であることがわかった.
|
|
ヒト過誤腫から樹立した間葉系幹細胞の性状の解析
小柳えりなさん(長崎大学歯学部4年生)
|
 歯槽骨再生療法の開発にはヒト間葉系幹細胞の性状を詳細に解析し,種々の分化調節機構を明らかにすることが重要である.私たちは,ヒトの間葉系幹細胞を解析するのに適したHamartomaの一例を経験し,その解析を行った.数種類の培養細胞を継代したが,その中でSV40 large T antigenを導入したHHC-K細胞は,骨芽細胞,軟骨細胞,筋肉,脂肪細胞などの種々の間葉系幹細胞への多分化能と自己複製能を保持していることが明らかとなった.私たちの樹立した細胞株の性状をさらに解析することで,歯槽骨再生療法開発の手がかりが得られると考えられた. 歯槽骨再生療法の開発にはヒト間葉系幹細胞の性状を詳細に解析し,種々の分化調節機構を明らかにすることが重要である.私たちは,ヒトの間葉系幹細胞を解析するのに適したHamartomaの一例を経験し,その解析を行った.数種類の培養細胞を継代したが,その中でSV40 large T antigenを導入したHHC-K細胞は,骨芽細胞,軟骨細胞,筋肉,脂肪細胞などの種々の間葉系幹細胞への多分化能と自己複製能を保持していることが明らかとなった.私たちの樹立した細胞株の性状をさらに解析することで,歯槽骨再生療法開発の手がかりが得られると考えられた.
|
|
繊維強化プラスチック型審美矯正ワイヤーの可動たわみ範囲の改善
南出 保さん(北海道大学歯学部6年生)
|
 現在,研究開発中のガラス繊維強化型プラスチック(FRP)構造を有する審美歯列矯正ワイヤーは金属ワイヤーとほぼ同等の曲げ強さを出しているが,曲率半径が小さい曲げに対しては破折に至る.そこでシランカップリング剤,重合条件の見直しにより,より大きなたわみまで変形可能になるように改良を試みた.破折はレジンとガラス繊維間の界面剥離が発端になるため,界面強さに密接に関連するカップリング結合と内部気泡の除去が物性の改良に最も効果的であった.結果,FRPワイヤーの破折たわみを従来の平均2.3mm 程度から3.3mm 程度まで増大できた. 現在,研究開発中のガラス繊維強化型プラスチック(FRP)構造を有する審美歯列矯正ワイヤーは金属ワイヤーとほぼ同等の曲げ強さを出しているが,曲率半径が小さい曲げに対しては破折に至る.そこでシランカップリング剤,重合条件の見直しにより,より大きなたわみまで変形可能になるように改良を試みた.破折はレジンとガラス繊維間の界面剥離が発端になるため,界面強さに密接に関連するカップリング結合と内部気泡の除去が物性の改良に最も効果的であった.結果,FRPワイヤーの破折たわみを従来の平均2.3mm 程度から3.3mm 程度まで増大できた.
|
|
|



 一般的に睡眠ブラキシズムは,夜間における顎機能運動と考えられている.睡眠時のブラキシズム運動は強力な咬合力を発揮し,歯の磨耗や歯周組織の破壊,顎関節の機能障害さらに咀嚼筋の異常活動を誘発する原因となっている.今回,睡眠時のブラキシズム運動を簡便に評価する方法を開発したので,その効果について報告する.被験者の上顎石膏模型に,ポリビニール製0.1mm厚のシートを加熱圧接して,ブラックスチェッカーを作製し,被験者に2日間就眠時に装着させた.各被験者の下顎頭の運動経路を調べるために,アキシオグラフを用いて運動を採得した.被験印象採得を行い,硬石膏模型を作製し,SAM咬合器に付着し,その咬合状態を観察した.グラインディングパターンは,ICPから始まる広い楕円形の後退運動として観察された.咬合誘導様式はCanine Dominance Grinding (CG), Canine Dominance Grinding with Balancing Grinding (CG+BG), Group Grinding (GG), Group Grinding with Balancing Grinding (GG+BG) の4つのカテゴリーに分類された.ブラックスチェッカーを用いることで,睡眠時のブラキシズム運動を評価し,機能的に調和した咬合の再建に応用できることが示唆された.
一般的に睡眠ブラキシズムは,夜間における顎機能運動と考えられている.睡眠時のブラキシズム運動は強力な咬合力を発揮し,歯の磨耗や歯周組織の破壊,顎関節の機能障害さらに咀嚼筋の異常活動を誘発する原因となっている.今回,睡眠時のブラキシズム運動を簡便に評価する方法を開発したので,その効果について報告する.被験者の上顎石膏模型に,ポリビニール製0.1mm厚のシートを加熱圧接して,ブラックスチェッカーを作製し,被験者に2日間就眠時に装着させた.各被験者の下顎頭の運動経路を調べるために,アキシオグラフを用いて運動を採得した.被験印象採得を行い,硬石膏模型を作製し,SAM咬合器に付着し,その咬合状態を観察した.グラインディングパターンは,ICPから始まる広い楕円形の後退運動として観察された.咬合誘導様式はCanine Dominance Grinding (CG), Canine Dominance Grinding with Balancing Grinding (CG+BG), Group Grinding (GG), Group Grinding with Balancing Grinding (GG+BG) の4つのカテゴリーに分類された.ブラックスチェッカーを用いることで,睡眠時のブラキシズム運動を評価し,機能的に調和した咬合の再建に応用できることが示唆された.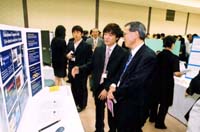 現在,インターネットは多角的に学習手段を結びつけ,新しいインタラクティブな教育環境を実現しようとしている.そこで,学生に要求される膨大な知識に対するアプローチとして,医学・歯学教育においてもe-learningを積極的に用いることを提唱したい.今回,学生の立場から,インターネットを介して,大学病院と地域の開業歯科医師との間で特に医療画像についてのカンファレンスを行うことを目的として開発された遠隔医療システムを学生教育支援へと応用した.本システムによるe-learningの試行を教員3名(小児歯科歯科医師)および,学生10名を対象として行った.システム利用許可を受けた学生は,いつ,どこからでも,画質の高い症例画像情報にアクセスでき,講義時間外でも,効率的に症例情報を検索・閲覧できた.症例画像を基に学生同士または教員を交えてのディスカッションをインターネット上で開催することもできる.教員側としては学生側の弱点・盲点等が容易に発見できるようになり,それをレポート学習におけるe-teachingや実際の講義に反映することにより,インターネットを用いた双方向教育が行えるということが示唆された.
現在,インターネットは多角的に学習手段を結びつけ,新しいインタラクティブな教育環境を実現しようとしている.そこで,学生に要求される膨大な知識に対するアプローチとして,医学・歯学教育においてもe-learningを積極的に用いることを提唱したい.今回,学生の立場から,インターネットを介して,大学病院と地域の開業歯科医師との間で特に医療画像についてのカンファレンスを行うことを目的として開発された遠隔医療システムを学生教育支援へと応用した.本システムによるe-learningの試行を教員3名(小児歯科歯科医師)および,学生10名を対象として行った.システム利用許可を受けた学生は,いつ,どこからでも,画質の高い症例画像情報にアクセスでき,講義時間外でも,効率的に症例情報を検索・閲覧できた.症例画像を基に学生同士または教員を交えてのディスカッションをインターネット上で開催することもできる.教員側としては学生側の弱点・盲点等が容易に発見できるようになり,それをレポート学習におけるe-teachingや実際の講義に反映することにより,インターネットを用いた双方向教育が行えるということが示唆された.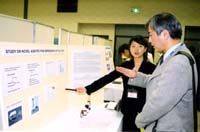 口臭は,その不快な感じから,広く認識されることがらのひとつである.一般的に,口臭の原因物質として揮発性含硫化合物があげられ,それは口腔内に存在する細菌によってタンパク質が分解されてできるものであることが知られている.そこで,この揮発性含硫化合物を低下させることにより,口臭を減少させることを試みることにした.含硫化合物の定量には,Halimeterを用いた.最初,含硫化合物と反応して不溶性,無臭の硫化亜鉛を形成する亜鉛化合物による試験を試みた.塩化亜鉛の溶液で処理することにより,揮発性含硫化合物の濃度を低下させることはできたが,塩化亜鉛の純粋なものをヒトに用いることは好ましいことではないと考えられた.そこで,食品または健康食品の中で亜鉛含量の多いものをインターネットで検索し,カキエキスが亜鉛を多く含有することを発見した.In vitro 試験でカキエキスが揮発性含硫化合物の濃度を低下させることを見出し,ヒトを対象にしたin vivo 試験でも,カキエキスが有効であることを見出した.したがって,口臭を除去するための洗口剤の成分として,カキエキスを用いる可能性が示唆された.
口臭は,その不快な感じから,広く認識されることがらのひとつである.一般的に,口臭の原因物質として揮発性含硫化合物があげられ,それは口腔内に存在する細菌によってタンパク質が分解されてできるものであることが知られている.そこで,この揮発性含硫化合物を低下させることにより,口臭を減少させることを試みることにした.含硫化合物の定量には,Halimeterを用いた.最初,含硫化合物と反応して不溶性,無臭の硫化亜鉛を形成する亜鉛化合物による試験を試みた.塩化亜鉛の溶液で処理することにより,揮発性含硫化合物の濃度を低下させることはできたが,塩化亜鉛の純粋なものをヒトに用いることは好ましいことではないと考えられた.そこで,食品または健康食品の中で亜鉛含量の多いものをインターネットで検索し,カキエキスが亜鉛を多く含有することを発見した.In vitro 試験でカキエキスが揮発性含硫化合物の濃度を低下させることを見出し,ヒトを対象にしたin vivo 試験でも,カキエキスが有効であることを見出した.したがって,口臭を除去するための洗口剤の成分として,カキエキスを用いる可能性が示唆された. 各種レジンセメントの取り扱い説明書では,補綴物の合着時においてセメントが完全硬化する前に余剰セメントを除去することを推奨している.しかし,完全硬化前,すなわち餅状期の4-META/MMA-TBBレジンセメントは粘弾性が非常に高いため,マージン部余剰セメントを除去した場合,マージン内部のセメント層を引きずり出す危険性が考えられる.そこで,その影響を調べる目的で実験を行った結果,マージンの適合が悪いと,また被着面が水で濡れていると,餅状期の余剰セメント除去よるセメント層の欠損が大きくなる可能性が高いことが示唆された.
各種レジンセメントの取り扱い説明書では,補綴物の合着時においてセメントが完全硬化する前に余剰セメントを除去することを推奨している.しかし,完全硬化前,すなわち餅状期の4-META/MMA-TBBレジンセメントは粘弾性が非常に高いため,マージン部余剰セメントを除去した場合,マージン内部のセメント層を引きずり出す危険性が考えられる.そこで,その影響を調べる目的で実験を行った結果,マージンの適合が悪いと,また被着面が水で濡れていると,餅状期の余剰セメント除去よるセメント層の欠損が大きくなる可能性が高いことが示唆された. 安全で快適な歯科治療を提供するためには“歯科治療の何に恐怖を抱いているか”を調査することが不可欠であり,国際化という意味においては国民性の差異を認識することも重要と思われる.そこで,本学および姉妹校でアンケート調査を実施した結果,日本では半数以上が抜歯を最も嫌いな処置に挙げており,歯科治療に対する不安感と抜歯処置の密接な関連が伺われた.また日本とイギリスでは処置が嫌いな理由として恐怖心を挙げる人が最も多く,フィリピンとタイでも2番目に多かった.これにより,今後は心理的要因への対策も重要であることが伺われた.
安全で快適な歯科治療を提供するためには“歯科治療の何に恐怖を抱いているか”を調査することが不可欠であり,国際化という意味においては国民性の差異を認識することも重要と思われる.そこで,本学および姉妹校でアンケート調査を実施した結果,日本では半数以上が抜歯を最も嫌いな処置に挙げており,歯科治療に対する不安感と抜歯処置の密接な関連が伺われた.また日本とイギリスでは処置が嫌いな理由として恐怖心を挙げる人が最も多く,フィリピンとタイでも2番目に多かった.これにより,今後は心理的要因への対策も重要であることが伺われた.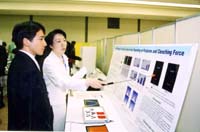 間接法による歯冠補綴物の作製では,通常,試適時に咬頭嵌合位より200〜300μm 程度高くなるため咬合調整が必要となっており,それを仰臥位で行うことがある.そこで,座位と仰臥位の両姿勢において,噛みしめ強さを変化させた際の咬頭嵌合位における咬合接触状態を比較し,仰臥位での咬合調整の妥当性について検討した.その結果から,片顎臼歯部の咬合接触の無い患者はもとより,咬頭嵌合位が安定している患者でもある程度の咬合力が負荷されないと咬頭嵌合位は安定しない可能性があり,咬合調整をする際には座位で行うことが望ましいと考える.
間接法による歯冠補綴物の作製では,通常,試適時に咬頭嵌合位より200〜300μm 程度高くなるため咬合調整が必要となっており,それを仰臥位で行うことがある.そこで,座位と仰臥位の両姿勢において,噛みしめ強さを変化させた際の咬頭嵌合位における咬合接触状態を比較し,仰臥位での咬合調整の妥当性について検討した.その結果から,片顎臼歯部の咬合接触の無い患者はもとより,咬頭嵌合位が安定している患者でもある程度の咬合力が負荷されないと咬頭嵌合位は安定しない可能性があり,咬合調整をする際には座位で行うことが望ましいと考える. 危険度の高い7つの競技において試合中のマウスガード(MG)着用が義務化されているが,その使用状況および選手の意識を調査・検討した.また,従来型(5mm)より薄型の試作MG(<3mm)を処方し,競技中の変化についても調査した.結果,練習中のMG着用率は競技・種目で差があり,試作MGは従来型に比べ呼吸・発声しやすく,練習中のMG使用率が上昇したことから,練習中のMG着用率の低さは従来型MGの不快事項に起因することが判明した.試作MGは従来型の問題点を解消し,選手の運動能力を向上させることが示唆された.
危険度の高い7つの競技において試合中のマウスガード(MG)着用が義務化されているが,その使用状況および選手の意識を調査・検討した.また,従来型(5mm)より薄型の試作MG(<3mm)を処方し,競技中の変化についても調査した.結果,練習中のMG着用率は競技・種目で差があり,試作MGは従来型に比べ呼吸・発声しやすく,練習中のMG使用率が上昇したことから,練習中のMG着用率の低さは従来型MGの不快事項に起因することが判明した.試作MGは従来型の問題点を解消し,選手の運動能力を向上させることが示唆された. 本研究では,歯周炎患者からのA.a.の検出率はprobing depthの増加に伴って上昇すること,患者から分離した菌株にはrough型集落が多いこと,rough型菌体には強いバイオフィルム形成能があることを明らかにした.さらに,バイオフィルム形成能と線毛関連性rcpAとrcpB遺伝子発現の関係を解析した結果,rough型菌株にはrcpAとrcpBの発現が認められるが,smooth型はほとんど発現しないことを見出した.これらの結果から,A.a.の線毛関連性遺伝子は,本菌が歯周局所でバイオフィルムとなって定着するために重要な役割を果たしていると考えられる.
本研究では,歯周炎患者からのA.a.の検出率はprobing depthの増加に伴って上昇すること,患者から分離した菌株にはrough型集落が多いこと,rough型菌体には強いバイオフィルム形成能があることを明らかにした.さらに,バイオフィルム形成能と線毛関連性rcpAとrcpB遺伝子発現の関係を解析した結果,rough型菌株にはrcpAとrcpBの発現が認められるが,smooth型はほとんど発現しないことを見出した.これらの結果から,A.a.の線毛関連性遺伝子は,本菌が歯周局所でバイオフィルムとなって定着するために重要な役割を果たしていると考えられる. 飼料形状によるマウス咬筋の表現型の変化にインスリン様増殖因子(IGF)が関与するかを調べた.マウスを離乳直後から固形飼料で飼育し,6カ月齢に達した時点で液状飼料に変え,さらに1週間飼育したところ,マウス咬筋のミオシン重鎖IIb(最も速筋型)mRNA発現量が増加していた.これは液状飼料に転換して1週間飼育したマウス咬筋に速筋化が起きたことを示している.また,液状飼料に転換したマウス咬筋のIGF-IおよびIImRNA発現量は共に減少していた.この結果より,IGFsの減少がマウス咬筋の速筋化と関係している可能性が示唆された.
飼料形状によるマウス咬筋の表現型の変化にインスリン様増殖因子(IGF)が関与するかを調べた.マウスを離乳直後から固形飼料で飼育し,6カ月齢に達した時点で液状飼料に変え,さらに1週間飼育したところ,マウス咬筋のミオシン重鎖IIb(最も速筋型)mRNA発現量が増加していた.これは液状飼料に転換して1週間飼育したマウス咬筋に速筋化が起きたことを示している.また,液状飼料に転換したマウス咬筋のIGF-IおよびIImRNA発現量は共に減少していた.この結果より,IGFsの減少がマウス咬筋の速筋化と関係している可能性が示唆された. ホワイトニング材の適用が金属修復物の電位挙動におよぼす影響について,歯科用金属合金を用いて検討を加えるとともに,実験の内容を理解し協力を得られた被験者の口腔内金属修復物について測定を行った.結果,使用したいずれの歯科用合金においても過酸化水素によって電位が貴になり,酸化が進むことが示された.また,口腔内における測定でも,過酸化尿素の適用によって貴になる傾向を示したところから,過酸化水素は歯科用金属に作用して酸化を進行させることが判明した.本研究から酸化を防止する保護材の開発が急務であることが示唆された.
ホワイトニング材の適用が金属修復物の電位挙動におよぼす影響について,歯科用金属合金を用いて検討を加えるとともに,実験の内容を理解し協力を得られた被験者の口腔内金属修復物について測定を行った.結果,使用したいずれの歯科用合金においても過酸化水素によって電位が貴になり,酸化が進むことが示された.また,口腔内における測定でも,過酸化尿素の適用によって貴になる傾向を示したところから,過酸化水素は歯科用金属に作用して酸化を進行させることが判明した.本研究から酸化を防止する保護材の開発が急務であることが示唆された. LPSによるマクロファージ活性化に伴うNO産生に及ぼす漢方成分と各種天然化合物の効果を,新たに作成した評価系(50%細胞障害濃度(CC50),NO産生の50%抑制濃度(EC50),有効係数(SI=CC50/EC50))を用いて比較検討した.漢方成分群は総じて細胞毒性は弱く,また,LPSによるNO産生促進を効率的に抑制した.これは呉茱萸湯において特に顕著であった.茶の抽出液群,及び各種新規天然化合物群では,多くが細胞障害活性を示す濃度でLPSの活性を抑えた.結果,漢方成分はLPSによって惹起される炎症反応を抑制することが期待される.
LPSによるマクロファージ活性化に伴うNO産生に及ぼす漢方成分と各種天然化合物の効果を,新たに作成した評価系(50%細胞障害濃度(CC50),NO産生の50%抑制濃度(EC50),有効係数(SI=CC50/EC50))を用いて比較検討した.漢方成分群は総じて細胞毒性は弱く,また,LPSによるNO産生促進を効率的に抑制した.これは呉茱萸湯において特に顕著であった.茶の抽出液群,及び各種新規天然化合物群では,多くが細胞障害活性を示す濃度でLPSの活性を抑えた.結果,漢方成分はLPSによって惹起される炎症反応を抑制することが期待される.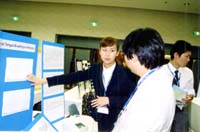 口腔に起因する口臭の原因である歯垢,舌苔に対し,歯ブラシと舌ブラシを行うことで,口臭に対しどの様な影響を与えるかを検討した.1日の口臭値(硫黄化合物:VSC)変動を口腔内清掃しない状態で,健康な被検者に対し計測した結果,起床時,食事後2〜3時間後に高い値を示すことが明らかになった.そのことから,昼食後口腔内清掃なしで2時間経過した時点で口臭を測定し,歯ブラシのみあるいは歯ブラシと舌ブラシを行う群とで,その後の低い口臭状態の持続を比較,検討したところ,舌ブラシの併用は低い口臭を持続することに効果的であった.
口腔に起因する口臭の原因である歯垢,舌苔に対し,歯ブラシと舌ブラシを行うことで,口臭に対しどの様な影響を与えるかを検討した.1日の口臭値(硫黄化合物:VSC)変動を口腔内清掃しない状態で,健康な被検者に対し計測した結果,起床時,食事後2〜3時間後に高い値を示すことが明らかになった.そのことから,昼食後口腔内清掃なしで2時間経過した時点で口臭を測定し,歯ブラシのみあるいは歯ブラシと舌ブラシを行う群とで,その後の低い口臭状態の持続を比較,検討したところ,舌ブラシの併用は低い口臭を持続することに効果的であった. 歯のホワイトニングを目的に,アナターゼ型二酸化チタンを含有した新しい歯磨剤の開発を試みた.光触媒作用を有するアナターゼ型二酸化チタンを合成し,そのX線回析パターンを作成後ピーク分析を行い,粉末X線データーブックをもとに同定し,本実験の試料として使用した.作成した歯磨剤をコーヒー,紅茶や食用色素で染色した布に塗布,紫外線を照射し,一日後,染色した布の脱色を測定した.結果,アナターゼ型二酸化チタン配合歯磨剤は優れた脱灰効力を持ち,また誰もが家庭で簡便に用いる事が可能なホワイトニング方法であることが示唆された.
歯のホワイトニングを目的に,アナターゼ型二酸化チタンを含有した新しい歯磨剤の開発を試みた.光触媒作用を有するアナターゼ型二酸化チタンを合成し,そのX線回析パターンを作成後ピーク分析を行い,粉末X線データーブックをもとに同定し,本実験の試料として使用した.作成した歯磨剤をコーヒー,紅茶や食用色素で染色した布に塗布,紫外線を照射し,一日後,染色した布の脱色を測定した.結果,アナターゼ型二酸化チタン配合歯磨剤は優れた脱灰効力を持ち,また誰もが家庭で簡便に用いる事が可能なホワイトニング方法であることが示唆された. テトラサイクリン着色歯に対する漂白処理の可能性を,牛歯によるディスク試料とハイドロキシアパタイト(HA)板を用いてin vitroで調べた.ΔE(色の変化)はディスク,HA板とも1回目の漂白処理においてのみ変化した.L*値(明るさ)はHA板で1回目の漂白処理においてのみ上昇するが,ディスクでは全ての漂白処理で変化しなかった.C*値(鮮やかさ)は1回目の漂白処理においてのみ,両方で低下した.結果,テトラサイクリン歯への漂白処理は有効であることがわかったが,漂白処理回数の増加が漂白効果の増大につながることは認められなかった.
テトラサイクリン着色歯に対する漂白処理の可能性を,牛歯によるディスク試料とハイドロキシアパタイト(HA)板を用いてin vitroで調べた.ΔE(色の変化)はディスク,HA板とも1回目の漂白処理においてのみ変化した.L*値(明るさ)はHA板で1回目の漂白処理においてのみ上昇するが,ディスクでは全ての漂白処理で変化しなかった.C*値(鮮やかさ)は1回目の漂白処理においてのみ,両方で低下した.結果,テトラサイクリン歯への漂白処理は有効であることがわかったが,漂白処理回数の増加が漂白効果の増大につながることは認められなかった.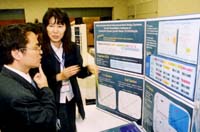 CTGFの様々な機能の解析のために,各種モノクローナル抗体を組み合わせ,3種のELISAシステムを確立した.それぞれの特徴は,1.CTモジュールとVWCモジュールを認識し,全長CTGFを測定するもの(全長CTGFの定量・解析に有用),2.N末端部のIGFBPモジュールとVWCモジュールを認識して全長CTGFを測定するもの(CTGFが断片化されて機能すると考えられる場合での解析に有用),3.VWCモジュールのみを認識し全長CTGFは認識しないもの(CTGFの断片化と,VWCモジュールを含む断片の動態を解析するのに有用),である.
CTGFの様々な機能の解析のために,各種モノクローナル抗体を組み合わせ,3種のELISAシステムを確立した.それぞれの特徴は,1.CTモジュールとVWCモジュールを認識し,全長CTGFを測定するもの(全長CTGFの定量・解析に有用),2.N末端部のIGFBPモジュールとVWCモジュールを認識して全長CTGFを測定するもの(CTGFが断片化されて機能すると考えられる場合での解析に有用),3.VWCモジュールのみを認識し全長CTGFは認識しないもの(CTGFの断片化と,VWCモジュールを含む断片の動態を解析するのに有用),である. 唾液カルシウム濃度はカリエスリスクファクターの一つと考えられるが,その測定は煩雑である.そこで,飲料水用カルシウム試薬であるEBTを用いると滴定操作におけるEDTA量によってカルシウム量を算出できることを利用し,唾液カルシウム量を簡単に評価する方法の開発を試みた.報告されている唾液内カルシウム量に近似する5種類のカルシウム溶液の色を赤から青へ変化させるのに必要なEDTA量から唾液カルシウム量への変換表を作成し,これにより5種類の唾液内カルシウム量が簡単に評価できるようになった.
唾液カルシウム濃度はカリエスリスクファクターの一つと考えられるが,その測定は煩雑である.そこで,飲料水用カルシウム試薬であるEBTを用いると滴定操作におけるEDTA量によってカルシウム量を算出できることを利用し,唾液カルシウム量を簡単に評価する方法の開発を試みた.報告されている唾液内カルシウム量に近似する5種類のカルシウム溶液の色を赤から青へ変化させるのに必要なEDTA量から唾液カルシウム量への変換表を作成し,これにより5種類の唾液内カルシウム量が簡単に評価できるようになった.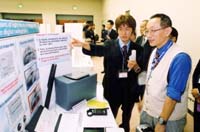 イメージングプレート(IP)方式のデジタルX線画像装置に使われるプレートは,照度650luxの室内光10秒の露光で48%に,光減衰による画像劣化が認められた.この光減衰への対応策として,遮光シートでプレートを被覆する方法を考案した.これにより撮影後のプレートは一度も室内光に曝されることなく画像化出来るようになった.人骨ファントムのパノラマX線写真を撮影,遮光シートを使用しなかった場合との画像の比較検討を行った結果,プレート遮光シートを用いることにより,通常の明るさで操作しても画像の劣化はみられなかった.
イメージングプレート(IP)方式のデジタルX線画像装置に使われるプレートは,照度650luxの室内光10秒の露光で48%に,光減衰による画像劣化が認められた.この光減衰への対応策として,遮光シートでプレートを被覆する方法を考案した.これにより撮影後のプレートは一度も室内光に曝されることなく画像化出来るようになった.人骨ファントムのパノラマX線写真を撮影,遮光シートを使用しなかった場合との画像の比較検討を行った結果,プレート遮光シートを用いることにより,通常の明るさで操作しても画像の劣化はみられなかった.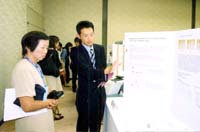
 歯槽骨再生療法の開発にはヒト間葉系幹細胞の性状を詳細に解析し,種々の分化調節機構を明らかにすることが重要である.私たちは,ヒトの間葉系幹細胞を解析するのに適したHamartomaの一例を経験し,その解析を行った.数種類の培養細胞を継代したが,その中でSV40 large T antigenを導入したHHC-K細胞は,骨芽細胞,軟骨細胞,筋肉,脂肪細胞などの種々の間葉系幹細胞への多分化能と自己複製能を保持していることが明らかとなった.私たちの樹立した細胞株の性状をさらに解析することで,歯槽骨再生療法開発の手がかりが得られると考えられた.
歯槽骨再生療法の開発にはヒト間葉系幹細胞の性状を詳細に解析し,種々の分化調節機構を明らかにすることが重要である.私たちは,ヒトの間葉系幹細胞を解析するのに適したHamartomaの一例を経験し,その解析を行った.数種類の培養細胞を継代したが,その中でSV40 large T antigenを導入したHHC-K細胞は,骨芽細胞,軟骨細胞,筋肉,脂肪細胞などの種々の間葉系幹細胞への多分化能と自己複製能を保持していることが明らかとなった.私たちの樹立した細胞株の性状をさらに解析することで,歯槽骨再生療法開発の手がかりが得られると考えられた. 現在,研究開発中のガラス繊維強化型プラスチック(FRP)構造を有する審美歯列矯正ワイヤーは金属ワイヤーとほぼ同等の曲げ強さを出しているが,曲率半径が小さい曲げに対しては破折に至る.そこでシランカップリング剤,重合条件の見直しにより,より大きなたわみまで変形可能になるように改良を試みた.破折はレジンとガラス繊維間の界面剥離が発端になるため,界面強さに密接に関連するカップリング結合と内部気泡の除去が物性の改良に最も効果的であった.結果,FRPワイヤーの破折たわみを従来の平均2.3mm 程度から3.3mm 程度まで増大できた.
現在,研究開発中のガラス繊維強化型プラスチック(FRP)構造を有する審美歯列矯正ワイヤーは金属ワイヤーとほぼ同等の曲げ強さを出しているが,曲率半径が小さい曲げに対しては破折に至る.そこでシランカップリング剤,重合条件の見直しにより,より大きなたわみまで変形可能になるように改良を試みた.破折はレジンとガラス繊維間の界面剥離が発端になるため,界面強さに密接に関連するカップリング結合と内部気泡の除去が物性の改良に最も効果的であった.結果,FRPワイヤーの破折たわみを従来の平均2.3mm 程度から3.3mm 程度まで増大できた.